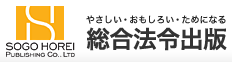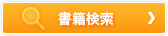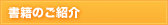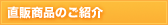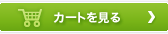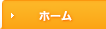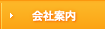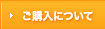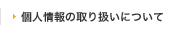■今週の市場展望
著者:青柳孝直
4/13号
『特集:淡々と進められる地方銀行の末期的合併劇』
- 4月6日の日経新聞朝刊一面は「関西・四国に広域地銀」の見出しが躍った。四国・トモニホールディングスの大正銀行の買収劇。昨年11月の「横浜・東日本銀統合」から以降、地銀再編のうねりはメガバンクを絡むかたちで加速し始めている。
- 1990年代の不良債権問題を経て、日本版ビッグバンが標榜され、都市銀行・信託銀行・長期信用銀行の集約が進み、3メガ銀行や巨大信託銀行が生まれた。そしてメガバンクは地銀の増資を引き受ける形態で関与を強めてきた。この構図が(表面的とは言え)地銀同志の再編の進展で変化し始めている。
- メガバンクにとっては2013年から適用が始まった国際規制「バーゼル3」の影響がある。自己資本の充実を厳しく求める内容で、金融機関同士の株式持ち合いが難しくなっている。更に今年6月には、金融庁と東証が定めたコーポレートガバナンス・コード(企業統治方針)に適用も始まり、持ち合い株に関して経済合理性について説明を求められることになる。メガバンクは(一旦は)所有する関連株式を売却せざるを得ない。
- 地銀・第二地銀は全国に105行が乱立し、再編は遅れている。世紀が変わった2000年からの推移をみると、20005年前後は経営の体力がある銀行が、不良債権に苦しむ銀行と合併・統合する“救済型”が一般的だった。しかし近年は大型再編こそ乏しかったものの、中堅行が人口減などによる経営環境の厳しさに危機感を募らせて結集する流れになっている。
- 日本の金融が3大メガバンク中心になった大きな理由は、IT機器の爆発的な発展により、「金融機関が(好むと好まざると)国際競争に晒される」からである。そして「国際金融(為替)+株式+保険」をも含んだ総合的な金融機関のみが生き残れる時代となってきたからである。今後は、潤沢な「人的資源+財的資源」をベースに、「世界の金融市場に対峙できるか」がポイントになってくる。
- 大胆に言えば、「現代社会において地銀の使命は終わった」と思うしかない。止めようもない国際金融の大きな変化の中で、金融庁主導による地銀の大々的な再編は、最終的に「3大メガバンクによる全地銀の系列化計画」の実施と思えば納得がゆく。
- (言い方は少々乱暴だが)「細かいのをまとめておいて、時期がきたら一網打尽にドカン」。地銀再編劇は、最終章の「3大メガバンクによる日本の金融機関の整備・統合」につながっていくように思う。
- 「3大メガバンクによる日本の金融機関の整備・統合」は、「マイナンバー制度の完成」および「国民の一人一銀行口座」にもつながる。税収に悩む日本国は、日本国民の資産をガラス張りにしたいのは明白である。いろいろな理屈をこねながら、法に張り付けた整理・統合は進んでいく。かくして最終シナリオは着々と完成に近づいている…
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円