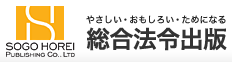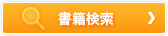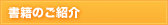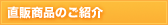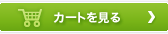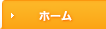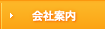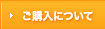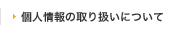■今週の市場展望
著者:青柳孝直
11/10号
『特集:日本の地方銀行の末期的合併劇』
- 11月4日の日経新聞朝刊一面は「横浜・東日本銀統合」の見出しが躍った。「攻めの広域再編」とある。だが、果たして地銀に生き残る道はあるのか。
- 1990年代の不良債権問題を経て、日本版ビッグバンが標榜され、都市銀行・信託銀行・長期信用銀行の集約が進み、3メガ銀行や巨大信託銀行が生まれた。反面、地銀・第二地銀は全国に105行が乱立し、再編は遅れている。
- 今更資産の大小で金融機関の優劣を決める時代でもないが、今回の横浜・東日本の統合により、総資産が10兆円を超えるのは、同横浜・東日本をトップに、以下福岡FG(14兆1000億円)、千葉(12兆円)、ほくほくFG(11兆1000億円)、静岡(10兆7千億円)となる。
- 世紀が変わった2000年からの推移をみると、20005年前後は経営の体力がある銀行が、不良債権に苦しむ銀行と合併・統合する“救済型”が一般的だった。2007年の福岡銀行が熊本ファミリー銀行(現・熊本銀行)、親和銀行(長崎県)を傘下の収めたのが典型例である。
- しかし近年は大型再編こそ乏しかったものの、中堅行が人口減などによる経営環境の厳しさに危機感を募らせて結集する流れになっている。だがこうした流れが「地銀の生き残りのための決定打」になるのか否か。
- 日本の金融が3大メガバンク中心になった大きな理由は、IT機器の爆発的な発展により、「金融機関が(好むと好まざると)国際競争に晒される」からである。そして「国際金融(為替)+株式+保険」をも含んだ総合的な金融機関のみが生き残れる時代となってきたからである。今後は、潤沢な「人的資源+財的資源」をベースに、「世界の金融市場に対峙できるか」がポイントになってくる。
- 未だに地銀は「地元の根ざす」ことを標榜する。ところが、新幹線・高速道等の交通網の爆発的な発達により、「地元意識」は次第に薄らぎ始めている。リニアで東京・名古屋間が40分になる時代。確かに地方にリニアが整備されるには相応の時間(50年程度)の時間が必要であろうが、この時間のハンディキャップをIT機器が補ってくれる。
- 金融庁主導による地銀の再編は、最終的に3大メガバンクによる全国の地銀の系列化の序章と思えば納得がゆく。(言い方は少々乱暴だが)「細かいのをまとめておいて、時期がきたら一網打尽にドカン」。地銀再編劇は、最終章の「3大メガバンク」による「日本の金融機関の整備・統合」につながっていくように思う。
- この「3大メガバンクによる日本の金融機関の整備統合」は、「国民総背番号制」および「日本国民の一人一銀行口座」につながる。税収に悩む日本国は、日本国民の資産をガラス張りにしたいのは明白である。かくして遠大なシナリオは着々と進行する…
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円