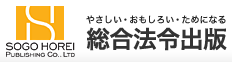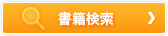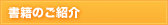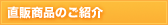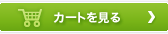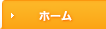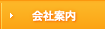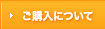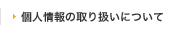■今週の市場展望
著者:青柳孝直
6/16号
『特集:4年に一度の世界のお祭り、W杯が始まった….』
- 1930年を第1回とする伝統のサッカー・ワールドカップ(W杯)の存在を知ったのは1982年。スペインでの第12回大会からだった。
- 当時ディーリングルームにいた自分は、西ドイツ(当時)の同僚から「2週間ばかり休みを取るからよろしく!」とのTELをもらった。「どこに行くんだ??」「何言ってんだよ、ワールドカップを見るんだよ!!」「皇帝・ベッケンバウワー様の最後のお姿を見にいくのさ」「ワールドカップ????ベッケンバウワー????」
- その時の(英語での)会話は今でもしっかり記憶に残っている。当時の日本では、サッカーはそれほど馴染がなく、「蹴球(しゅうきゅう)」という日本語名もまかり通っていた。当然にしてプロチームもなく、釜本・杉山といった実業団の名選手を中心に、メキシコ五輪で銅メダルを取ったことは知っていても、それがほぼ全てだった。
- 「サッカーの国際試合はある意味、国対国の戦争だ」ということもよく聞かされてはいた。実際に戦争が起こった例もある。だがそれから10年後、“たかがサッカーで”戦争が起きる意味がようやくにして理解するようになっていく。
- 1994年、日本にJリーグが発足、 日本にプロサッカーが根付いていく。そして大きな目標は「W杯に出る」ことも認識するようになる。日本がW杯に初出場するのが1998年のフランス大会からだが、魅入られるようにサッカーにのめり込んでいった。国対国の1時間半の戦いは息を飲むような“魔力”と“迫力”があった。
- 21世紀に入って、日本のサッカーも徐々に国際化していく。Jリーグに海外からの選手の参入があったことも大きいが、中田英寿を先頭に、日本選手の海外移籍が相次いだことも大きかった。今回で5大会連続出場となる日本チームが「優勝を目指す」と言っても、笑い話でなくなり始めている。
- そして今回の大きなトピックスとして、12日午後5時(現地時間)からのブラジル対クロアチアの開幕戦で、西村雄一主審(42)、相良亨(37)名木利幸(42)・両副審の日本人トリオが審判を任されたことである。
- 西村主審は前回の南アフリカ大会の準々決勝・オランダ・ブラジル戦で、相手選手を踏みつけたブラジルのフェリペトロ選手を退場処分にした。球際の競り合いが激しい国際試合での冷静な判断が欧州メディアに称賛された。開幕戦に日本人トリオの審判団が選択されたことは日本サッカー界にとって、まさに“金字塔”ではあった。
- 田中、ダルビッシュ、岩隈等の日本人投手の活躍が目立つ米大リーグ(MLB)や、現地時間12日から始まった全米プロゴルフ選手権も、W杯の前では影が薄い。そして特にサッカー盛んな欧州では、大会期間中、金融市場もパタリと動きを止める。かくして以降約1ヶ月、世界はW杯という4年に1回のお祭りを中心に動いていく…
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円