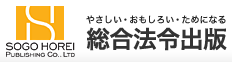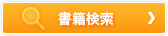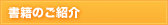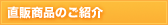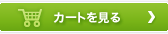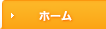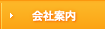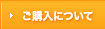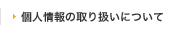■今週の市場展望
著者:青柳孝直
3/24号
『特集:「NHK朝ドラ」という純日本的な世界』
- NHK朝ドラ、正確に言えばNHK連続テレビ小説は、1961年「娘と私」(獅子文六原作)でスタート、以来半世紀を超え、今年3月31日からスタートする「花子とアン」で90作目となる。月~土曜15分の放送が基本で、現在は毎朝8時を中心に、地上波、BSを含めて1日4回放送している。
- 日本人は朝ドラという形式を至極当然のように思っているが、1日15分のドラマを、土日を除いて毎朝放送するという形式が、半世紀も続いてきたという例は世界にない。
- 一般論として、テレビドラマ視聴率は、朝ドラに限らず下降傾向をたどっている。インターネットやゲーム等を通した娯楽が多様化し、欲しい情報が瞬時に手に入る現代社会において、毎週1回の連続ドラマや毎日15分だけの朝ドラを見続けるというのは、今や“時代遅れの”受容形態である。また放送時間に合わせて視聴する形態は薄れ、ネットを使った「オンデマンド方式」が主流になりつつある。
- そうした時代の流れに逆らった方式が続いてきた最大の理由は、朝ドラが趣味や娯楽というよりも、日本人の「生活の一部」であり、「(一種の)日課」のようなものになったからである。要は朝ドラは「(日本人の)生活のリズム」を醸成してきた。それが毎朝15分しか見られないという「不自由さ」を受け入れた理由でもある。
- 朝ドラが受け入れられてきたもうひとつの理由は「先を急がない」ことにもある。劇的な展開となれば、15分では到底描き切れない。その点朝ドラは「毎日同じ人に出会う」ことに意味がある。極端に言えば、「毎朝家族に顔を合わす感覚」に近い。
- 基本的に言えば、朝ドラに重要なのは「事件」よりも「人」である。毎朝元気に仕事に向かう気持ちにしてくれる明るい笑顔や、仕事から帰ってほっとした気分にさせてくれるあたたかい微笑(ほほえみ)が見たい。従って、女性に焦点を当てた朝ドラの代々のヒロインはスーパーウーマンである必要がなかった。
- 83年11月12日に「おしん」が記録した62.9%は、62年にビデオリサーチが調査を開始して以来、史上最高率とされている。ただそうした“(朝ドラの)劇的な展開”は異例で別格である。現在の朝ドラに過剰なドキドキ感は不要である。
- その意味で(今月で終了する)NHK大阪制作の「ごちそうさん」は朝ドラの典型ではあった。劇的な展開はなくとも、人から感謝の言葉を聞くことを生きがいとした主人公の思いに触れることが、視聴者の日々の生活を明るくしてくれた。
- 今や伝説のシリーズ「水戸黄門」「男はつらいよ」「釣バカ日誌」等も、朝ドラと同じ線上にあるように思う。「最後の結果は分かっている」「筋書きはいつも同じ」という安心感が視聴者に「癒し」を与えてくれるのである。今や日本の日常生活の一部となった朝ドラは、時代が変わっても、IT時代がいかに進捗しようとも、永遠に不滅と思う。
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円