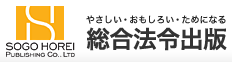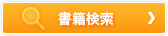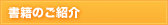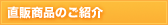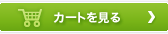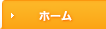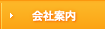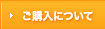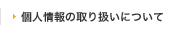■今週の市場展望
著者:青柳孝直
11/25号
『特集:「食品偽装」のロジック』
- まず「偽装」とは何か。角川・国語辞典に拠れば、「みせかけること」「ごまかし」「カモフラージュ」と定義する。
-
「食品偽装」が問題になったのは、10月下旬。阪急阪神ホテルズで大規模な食品偽装が発覚して以来、各地で次々と同様の例が明らかになった。この際だからと、“便乗する”ムードが広がり、全国的な流れになった。
帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニの「ホテル御三家」や、高島屋、三越伊勢丹、大丸松坂屋、そごう・西武の「四大百貨店」、さらに美濃吉やつな八などの老舗でも偽装が発覚した。 -
なぜこのような偽装が蔓延したか。簡単なロジックである。ホテルなどの料理人は調理は勿論、食材の調達も任せられる。経営者側から安い食材を仕入れて高く売ることを要求される結果、偽装食材を使って経営者の要求を満たすこととなった。
また高級店の料理人は、別のホテルや旅館のレストランから引き抜かれるのも日常茶飯事。その際、食品偽造のノウハウまで移籍先に持ち込むことが多かった。また料理人が引き抜かれても、残ったスタッフに偽装のノウハウが伝承された。 - かくして食品偽装が拡散していく。「業界の慣習」として偽装を正当化してきたのが現在の業界の姿ではある。一方消費者は、ホテルや百貨店のブランド価値に対して割高な料金を支払ってきた。その絶対的な(ブランドに対する)信頼が崩れることにはなった。
- こうした偽装がまかり通ってきた最大の原因は法律の不備にあった。スーパーなどで市販される食品については食品衛生法や食品表示法が適用される。しかし外食産業の場合は「対面販売のため店員から直接説明を聞ける」等の理由で、この法律が適用されない。
- 外食産業の偽装を取り締まる法律としては、不正競争防止法と景品表示法がある。前者は刑事罰を定めてはいるが、先例に乏しく、責任の所在が経営者、仕入れ担当者、調理担当者のうち誰なのか、曖昧で立件が難しい。
- 一方、商品の不当表示を罰する景品表示法は先例が多く、今回の一連の偽装はこの景品表示法が適用し易い。しかし罰則は軽く、消費者庁から是正指導があるに過ぎない。企業側は指導に従えばそれ以上の責任を問われることもなく、返金義務も発生しない。
- この一連の偽装問題が起きて「ほたるいか(産地)偽装」問題を思い出した。ほたるいかは富山湾の特産とされている。特に滑川(なめりかわ)ブランドは築地市場でも定着している。要は富山湾以外の県で獲れたほたるいかを富山湾産として販売し、その産地偽装が問題となり、富山県知事が記者会見をするまでの大問題に発展した。
- 結局、安くて美味しいものをそれなりの店で食していれば問題がないように思う。食の安全・世界一の日本における偽装問題提起は、日本が裕福な国である証左と思うが…
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円