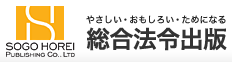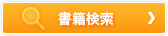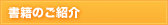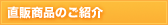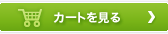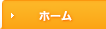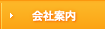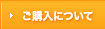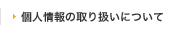■今週の市場展望
著者:青柳孝直
5/01号
『特集:居酒屋の経済学』
- 酒を(本格的に)飲み出したのは、当然ながら大学時代である。今は亡き叔父が、銀座・ソニービル近くの外堀通り沿いにやっていたスタンドバーで、今日は入学のご褒美だ、ご馳走してやる、さぁ飲め!と出されたのがサントリー・オールドのコークハイ(ウィスキーのコーラ割り)だった。
- それが自分の酒人生を決定的にした。以来、サントリー系ウィスキーのハイボール(ウィスキーの炭酸割り)一筋の人生である。つい最近、サントリー角瓶の炭酸割を、これをハイボールと呼ぶんだと、あたかも新商品の如くの扱いをしているが、元々は1970年代前半から営々として飲まれてきた手法である。今更何言ってんだか、って思う。
- 自分の学生時代はほんとにあきれるほど飲んだ。吐いては強くなっていった。こんな言い方をすると世の教育ママ連中には眉を顰められるとは思うが、吐くほど飲むからアルコールに対して免疫性ができるのである。当たり前の“実戦論”である。
- ワセダの街、高田馬場は学生に対して至極寛大だった。高い酒を安く、またつまみも高級なもの、言葉を変えれば酒に合うような“(通の)大人の味”をさりげなく供してくれた。そんな環境で育ったせいか、酒を飲む時は余り食べない。そして食べる時は飲まないという習性が身についてしまった。自慢じゃないが、食べながらダラダラ飲むなんて芸当は自分にはできそうにもない。
- 1980年代後半から居酒屋チェーンが流行り出した。「(ダラダラ)食べながら飲む」ことをテーマにしているから、とにかく酒が薄い。そして不味い。酒の薄さは、自分のような呑兵衛にしてみれば“酒の味のする水”である。つまみも「電子レンジでチン」のパターンのオンパレードだから、脂っこいだけで、さっぱり美味くない。
- 一時大流行した「村さ来」「つぼ八」「和民」などの有名チェーンを、とりあえずと行ってみたが、期待にたがわずガッカリするばかりだった。こんなんじゃそのうち若者も離れていくわ、などと思っていた。
- 予想にたがわず、居酒屋市場は1992年の約1兆4600億円をピークに減少しており、2010年には9946億円まで落ち込んだ。市場関係者では、若者のアルコール離れを原因に上げているが、その実は市場関係者が若者に“本当の酒の味”“本当の酒の飲み方”を教えなかったツケがきているのだと思う。
- 現在住まいしている佃界隈は、銀座・六本木に近く、築地市場も近い。日本で一番美味しいサカナが集まる築地のすし、というより酒のつまみは極端に安価で最高に美味い。特に“まかない”で出された料理を供されると、酒がドンドン進んでいく。
- 若者が酒離れをしているのではないと思う。そうした安価で美味しいつまみがあると知れば自然に若者はついてくる。日本式の想定内の考え方では何も変わらないのである。
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円