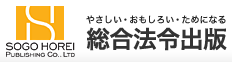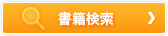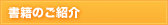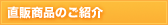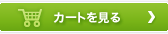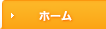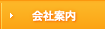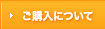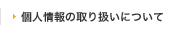■今週の市場展望
著者:青柳孝直
7/11号
『特集:「不透明で、意味不明な円高」を検証する』
- 1ドル80円前後の円高が続いている。「日本の国力が衰えている」といわれる中で、なぜ円は長期的に上昇を続けてきたのか。今週は「購買力平価」ならびに「実質実効レート」をベースに検証してみたい。
- まず購買力平価は「為替レートは2つの国の通貨の購買力(モノを買える価値)が同じようになるように決まる」のを基本としている。言葉を変えて言えば、インフレ率の高い国の通貨は、同じお金で買えるモノが少なくなるので、長期的には価値が下がる。
- この論理から言えば、「低いインフレ率を反映した結果、円の価値は相対的に上昇してきた」のである。例えば、90年以降の物価上昇が日本では1割弱。逆に米国では7割。これほど歴然とした差があれば、円高・ドル安の流れになるのは自然だった。そうでなければ、日本人は値上がりした米国商品を買えなくなっていたのである。
- 但し、この購買力平価の考え方は、様々な要因が入り乱れて動く短期予想にはそぐわない。しかし長期的予想においては不可欠な、重要な要因となっている。「為替はモノとモノとの交換価値なので、長期ではインフレ率によって左右される」からである。
-
では購買力平価から考えた長期の為替予想はどうなるのだろうか。「日本のインフレ率が相対的に低い状況が続くなら、少子高齢化や東日本大震災で国力が弱体化しても、長期で円高基調が続く」ことになる。但し、物価下落の要因となっていた賃下げが限界に来ているを考えれば、転換点も近いと考えることはできる。
購買力平価と同じようにインフレ率の格差を調整して算出された為替レートが「実質レート」である。これをユーロや人民元など多くの通貨を貿易量に応じて加重平均したのが「実質実効レート」である。 - 今回の円高は「95年以来の円高」と言われているが、実質実効レートでは95年よりは3割程度円安であり、上昇リスクは残っていることになる。80円の3割とは約24円。理論上とは言え、55円程度の円高・ドル安の可能性が残っていることにはなる。
- いずれにしても、購買力平価の考え方が理解できれば「高金利通貨に投資すると得とは言えない」ことが解ってくる。高金利の国はインフレ率が高いことが多く、「通貨の急落で高金利のメリットが失われるリスク」が付きまとうからである。
- 但し、以上の考え方は「基本データに沿って、金融市場が正常に機能する」ことを前提としている。しかし現在の世界経済には、社会主義市場経済と言われる極めて異質な経済システムを敷く、“中国という不純物(紛い物)”が控えている。
- 欧米もそして日本も、市場経済という魔物にさんざん苦労してきた。しかし中国は、市場経済の負の側面、つまりは“暴力的な行き過ぎ”を経験していないし、拒否しようとさえしている。結局、21世紀の異質な大国・中国の動向からは目が離せないのである。
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円