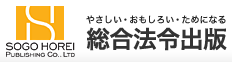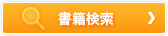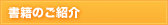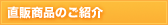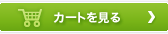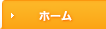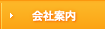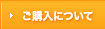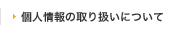■今週の市場展望
著者:青柳孝直
2/07号
『特集:「中国GDP世界第二位」の実態を検証する』
-
1月20日、中国国家統計局は、2010年の国内総生産(GDP)が実質で前年比10.3%増となったと発表した。年間の成長率が二桁になったのは07年以来3年振り。
大和証券の試算によれば、中国の10年の名目GDPはドル換算で5兆8895億㌦。また同社の推計で日本の10年の名目DGPは5兆4778億㌦で、中国を4000億㌦下回る。日本は42年間にわたって保ってきた世界第二位の経済大国の地位を譲ることになった。 - 今回の発表から、日本が身近に感じ始めていた中国経済の脅威が現実なものになったことにはなる。しかし日本は本当に中国経済に凌駕されたのだろうか。「中国経済から垣間見える現実」について考えてみたい。
- 中国は今や「世界の工場」と呼ばれ、世界一の輸出大国になったのは間違いない。しかし「世界の下請け大国になっただけである」という言い方もできる。何故なら、高度成長期の日本には、トヨタ、日産、ソニー、パナソニック等の国産ブランドが世界を席巻した。しかし現在、中国発のブランドで世界に通用しているのは皆無だからである。
- そして「下請け大国」という構造が、中国のGDPを実力以上に大きく見せる結果になっている。例えば日本企業が中国の工場で生産した商品は、中国のGDPにカウントされる。また公称で13億人と言われる人口の規模を考えれば、日本よりも総生産が多くて当たり前。国民1人当たりでは、日中間には10倍以上の開きがあることになる。
- とは言え、世界的な金融危機の後遺症から抜け出せない日米欧を尻目に中国は、2011年も二桁近い成長が予想され、世界は中国を「世界経済のエンジン」と位置付けてはいる。だが、一部では中国経済がどこかで急減速するとの見方も少なくない。
- 昨年8月、中国が世界第二位の経済大国になることが確実視され、いつ米国を抜き去るかに注目が集まる中で、米誌「フォーブス」で「中国が米国を超えられない五つの理由」という論文が発表され、大きな話題になった。
- その五つとは「水資源の欠乏」「国内エネルギー資源への不安」「食料生産の限界」「加速する高齢化」「独裁政治の限界」。(但し中国では、五番目を外し、「四つの理由」として発表されている)。同論文では、中国は、医療・年金等の社会インフラは未整備のまま、経済成長の条件は急速に失われる。それが中国の実情であると喝破している。
- 「世界経済はアイドル(崇拝対象)が現れては消える」と言われる。1980年代の日本、1990年代のアイルランドなどの欧州周縁国、そして2000年代の米国。経済の強さの裏には必ずひずみが生まれ、永遠には持続しない。
- 現在の経済社会は否応なく中国経済への依存度を深めている。従って、世界経済は中国の持つリスクと共存する世界に身を置いていることになる。結局「世界第二位」の中国は実は怖くはないのである。怖いのは「経済が崩壊し始めた時の中国」なのである。
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円