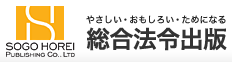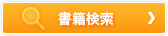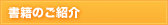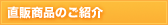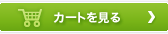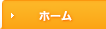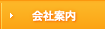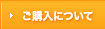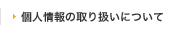■今週の市場展望
著者:青柳孝直
9/13号
『特集:30年振りの「株式の死」』
- 「株式の死、再来か」。米メディアで最近、このような論調が目立っている。今から約30年前の1979年8月、米経済誌・ビジネスウィークは「株式の死(ザ・デス・オブ・エクイティーズ)」と題した巻頭記事を掲載した。
- 1970年代の米はインフレが進み、高い失業率に苦しんだ。大型優良株のバブルが崩壊し、米国株は長期低迷を余儀なくされた。デフレ不安に悩む現在の市場環境は、当時とは土壌が全く逆である。
- ただ個人を含めた投資家が上値の重い株式投資に魅力を感じられなくなり、株式に対するリスクを敬遠する動きが広がっている点は似通っている。相場用語でいう「戻り売りパターン」に嫌気さしているのである。
- そして日本の株式は、米国以上の悲惨な状況になり始めている。日米株式市場は連動していると言われてきた。しかし6月4日の菅直人首相指名と前後して、日経平均株価はNYダウ平均についていけなくなった。そして6月27日のトロント・サミット以降は、米欧が自国通貨安の容認のスタンスを見せたことで円高が加速した。
- 「菅首相は市場への感度が鈍い」とみて進んだ円高&株安。それに続き壊し屋・豪腕・小沢の登場で、長期金利上昇を危惧する声が広がり、日本の金融市場は悲観材料のオンパレードとなっている。包括的な閉塞感が蔓延している。
- 「雇用、雇用、雇用」と菅首相は連呼する。しかし雇用を生み出すための確たる政策は提示されていない。経営者の多くは、生まれ育った日本にいたいという「感情」はあっても、「勘定」の上では完全に日本から離れてしまっている。言葉を変えれば、日本の企業が「日本にいること」に懐疑的になってしまっている。
- 戦後の日本では「勤勉で安価な労働者の確保」という意味では優位性があった。しかし現在では、安価な労働力を潤沢に持つ新興国の台頭で、いつの間にか日本は高コストの国と位置付けられるに至っている。
- 一方、市場としての日本を考えれば、少子高齢化と人口減が進展する中で、国内だけの事業展開ではもはや絶望的な状況にある。円高の煽りで、外国に生産拠点を置き、労働者が外国人、出荷先も海外であるなら、高い法人税を徴求される日本に本社を置く理由がない。そして、その状況の中では「雇用が生まれる」はずがない。
-
昨今の急激な円高への対応の遅さや、バラマキ優先の経済政策で、現政権に対する経済界の失望感は明白である。政治主導を進めるはずの政治家は優秀な人物のはずだが、金融をはじめ経済、とりわけ市場に対する感覚が鈍く、危機感が薄いように映る。
かくして、米国で言われ始めた「30年振りの株式の死」は、実は空洞化現象が顕著で、再上昇のキッカケを掴めない日本で深刻になり始めているのである。
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円