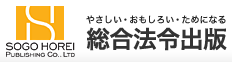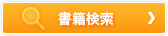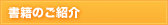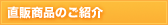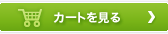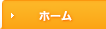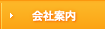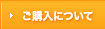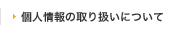■今週の市場展望
著者:青柳孝直事務所
11/09号
『特集:出版不況を検証する ~電子書籍「キンドル」の脅威~』
-
10月22日、インターネット小売最大手、米アマゾン・ドット・コムは、2009年7~9月期決算で、純利益が前年同期比69%増の1億9900万ドル(約180億円)であったことを明らかにした。
電子書籍端末「キンドル」をはじめ、幅広い分野で割安な商品を揃えたことが好結果につながったとしている。キンドル販売台数は開示されていないが、同社は世界展開を始めており、出版や流通のネット化が一段と進むとの見方が広がっている。 - 同22日、米書店協会は、米小売最大手のウォルマート・ストアズやアマゾン・ドット・コムなどが、オンライン販売で繰り広げている書籍の低価格競争をめぐり、米司法省に調査を依頼した。
- 同上二社は、10月中旬から年末商戦の目玉として通常25~35ドル(2300~3200円)程度の新刊本の人気作を9ドル以下に値下げし、他社も追随している。米書店協会では、一連の低価格販売について「違法で略奪的な価格形成」であると主張している。
- 当該価格競争では、まずウォルマートがネット販売限定で10種類の新刊本を一律10ドルで販売するキャンペーン開始。これに対しアマゾンは、同様の価格を10ドルに下げると、ウォルマートは9ドルに再値下げ。ディスカウント専門店大手のターゲットが参戦したことで拍車がかかり、現在は3社が9ドルを割る価格を設定している。
- こうした世界的な書籍価格割引競争の中で、日本の出版不況も深刻である。有名雑誌の休刊が相次ぐなど、インターネットの普及や少子化など、環境の変化による出版不況に歯止めがかからない。アマゾンなど世界的なネット小売大手が日本語版書籍の低価格発売を始めれば、その影響は深刻なものとなる。
- 日本の書籍界では、年間7万冊、1日あたり約200冊の新刊が発売されてている。ところが、書店からの返品率は40%。「委託販売制」のため、書店の在庫リスクが小さい反面、収益性も低い。中小規模の書店ほど経営は厳しく、書店数が減ってさらに市場が縮んでいくという、“スパイラル”現象となっている。
- 「活字を電子媒体で読む時代の到来」は“想定内”で、格段驚くべきことではない。とは言え、ジックリ手にとって本を熟読するという習慣は、人間形成には必要である。また書籍には紙の質感や装丁、イラストなど、文字のコンテンツ(情報の内容)にとどまらない文化が宿っている。日本の家屋には木製・本箱(or本棚)が似合い、畳と本箱の世界は日本独特のものではあった。
- 時代の転換期で、どの業界も問題を抱える。ただ出版不況の根本は、本の内容(=書き手の能力)に帰結するのかもしれない。ギッシリと内容が詰まった本は、手にとってジックリ読みたい。書き手の端くれとして、十分考えなければならない問題である。
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円