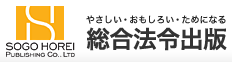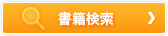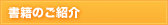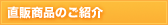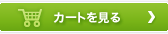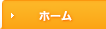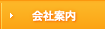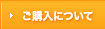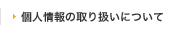■今週の市場展望
著者:青柳孝直事務所
10/05号
『特集:JAL(日本航空)を包み込む暗い闇』
- ここ5年、読んだ本は何かと問われれば、山崎豊子氏の著作である。「暖簾(のれん)」「ぼんち」「華麗なる一族」「二つの祖国」「女系家族」「白い巨塔」「不毛地帯」等など。テーマは重いものばかり。内容が重厚で、簡単には読みこなせない。
- 凄いのは事前調査が緻密で、徹底している点である。仮名を使ってあるが、実名がすぐに分かる内容となっている。言い換えれば、「ノンフィクションに近いフィクション」。戦後の日本経済の裏側を描いた傑作揃いである。
- その一連の著作に「沈まぬ太陽」がある。ご存じのように、日本航空(以下JAL)の実態を描いたものである。文庫本では5部建てになっており、一部&二部は組合の実態、三部が日本の航空史上最大の惨事となった御巣鷹山の墜落事故、そして四部と五部は、JALの財務状態を含む経営実態を克明に描いたものとなっている。
- ここ最近深刻な経営難が問題となっているJALは、「(日本の)ナショナル・フラッグ」の地位を享受してきた。つまり名目的にも実質的にも「日本の国営航空」の地位にあった。そして日本国民には「JALに乗せて戴いている」という認識があった。
- ただそうした「親方日の丸」の意識は、会社経営を杜撰なものにしていった。特に1970年代から80年代前半まで続けられた石油輸入にからむ(無理矢理な)為替予約取引(ドルの先物買取引)での推定4千億円超の為替差損が現状まで尾を引いている。
- 1985年9月のプラザ合意以降の急激な円高から、一連の為替差損が表面化していくことになるが、「沈まぬ太陽」ではその専門的な部分の描写に多少の曖昧な部分があるものの、日本有数のトップ銀行が仲介して、政界の闇資金との相対取引(ドルの先物売り)があったことを暴露している。
- 要はJAL本体で「政治が介入した不明朗な部分があった」のは否めないようである。確かにJALは、終戦後25年は国営航空会社として君臨していたが、一方で営利企業としての企業努力がなされることがなかった。結果、「腐った小さなリンゴが箱全体のリンゴを腐らせる状態」になっていったのは自然の理だったのかもしれない。
- 日本のバブル時代以降、日本国民の海外旅行が当たり前となり、同時に客室乗務員(当時はスチュワーデス=スッチー)が持て囃されたが、一方JALの実態は、航空機内部の乗客一人当たりの仕切り面積を最大限にまで狭くし、稼働率を上げようと躍起となっていた。エコノミークラスの乗客は、あたかも「ブロイラー状態」だった。
- 「JALに乗せて戴く」時代から「航空会社を選ぶ」時代になった。そうした選択が自由になって日本国民は“(国民を荷物の如く扱ってきた)国営航空”を拒否し始めた。種々の解決案が論議されてはいるが、小手先のJAL改革は難しいと思う。自民党が崩壊したのと同様、JALの全面解体修理の時期であると思う。
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円